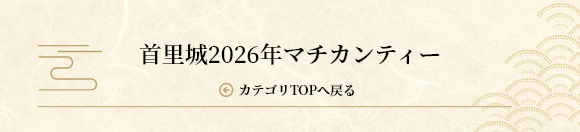メニュー
ホーム > 首里城復興へのあゆみ > 首里城2026年マチカンティー > 若手職人インタビュー #13
若手職人インタビュー #13


―家業である「窯元 やちむん家」を継いで、シーサー職人になられたきっかけを教えてください。
元々は福祉関係の大学に通っていて、将来は社会福祉士を目指していました。でも大学3年生のときに、親方(父親の新垣 光雄さん)が京都の清水寺に奉納する龍を制作しているのを工房で見てすごくかっこいいなと思って、自分でも作ってみたいと思うようになりました。その龍は大きさが2m80cmあって作品としてもすごいし、清水寺という誰もが知る場所に置かれるということもすごいことだなと。
それまでも親方のシーサーが沖縄で一番すごいと思っていたんですが、それは親方だからできることであって、自分とはあまり関係の無いことだと思っていたんです。でも、この龍がきっかけで、自分もこんな職人になりたいと思うようになって、21歳の時に弟子入りという形で工房に入りました。
―その際、お父様はどのように感じられましたか?

(光雄さん)それはもう、いちばん嬉しかったですよね。
だけど大変な仕事だから続けられるか心配もあったんですけど、やってみたら彼はすごく良いものを作るんですよ。
うちは「やちむん家」としてメンバーでやってはいるんですが、職人ひとりひとりがブランドというか、それぞれのカラーがあるので、私からこうやれああやれっていう指導はないんです。
ものづくりする人って、見ればだいたい分かるんですよ。自分でいろんな作品を見て、良いところを見つけて取り入れたり試行錯誤でやっていくのが基本というか。
私の親父もこうやれああやれって教えなかったですし「本気で分からないんだったら、お前は分からない」って、もうバッサリでしたから。
そういう厳しい世界ではありますが、自分の感じるものを自由に表現して伸び伸び作品を作っているなと思います。

私の時代にはなかったことですが、若手の職人で集まって交流したり、SNSで世界中のいろんな画像や動画を見たりして、自分で考えて悩んでいろんな答えを拾ってきますよね。
若いから未熟とかではないんです。とっても柔らかいからいろんなことを吸収するし、彼はハートがすごいから良い作品を作るんですよ。
同じ職人として刺激を受けますし、父親としても、とても嬉しいです。
―今回、首里城正殿の屋根に設置される「鬼瓦」を制作されましたが、どのような経緯で鬼瓦制作に携わることになったのでしょうか?

※鬼瓦⋯正殿屋根に配置される装飾瓦。首里城では「鬼」ではなく「獅子」の造形。
阿吽形の2対を正殿正面と背面に合わせて4体設置。(令和7年5月設置済み)

以前から「やちむん家」として沖縄県内で大きいシーサーを作っていたので、その技術面と、工房に職人が4名いて作業を分担できるということで、今回のお話をいただきました。試作を含めて4名でそれぞれ2体ずつ、合計8体を制作しました。
今回の鬼瓦は、体を上下に分けて制作し最終的に組み合わせるという構造で、親方はこれまでにもそれと同じ工法で大きなシーサーを作ったことがあったんですが、私はこれまでやったことがなく初めての挑戦でした。
シーサー職人として首里城の復興にこうした形で携われたというのは、とても名誉なことですし光栄だなと思います。
―鬼瓦の具体的な制作工程と、難しかった点があれば教えていただけますでしょうか?

まず土作りからなんですが、どういった土が今回の鬼瓦を作るのに適しているか全く分からない状態からのスタートでした。今回、うるま市と恩納村の土も一部使用するということで、普段工房で使っているベースとなる土に沖縄県の土をどのぐらいの割合で入れるか、また釉薬の色が出やすい割合はどれぐらいなのか、何度も試作をして、焼いた時に歪みが出ないかも確認したり、細かい計算もしなければいけなかったので、そこがとても難しかったですね。
その次が造形で、最初は石膏で作った型枠を使って作っていく想定だったんですが、私たちは普段から大きいシーサーを“手びねり”という手法で作っているので、この大きさなら手びねりで作った方が良いものができるのではないかということで提案させてもらったんです。それが通って、今回はすべて手びねりで作っています。

※手びねり:粘土を指先で伸ばしながら形を作っていく技法
体が上下に分かれているので、まず下の部分を作ってから上の部分を乗せるんですけど、乗せた時に上下の境目が見えないよう、上の大きな毛の部分がきれいに境目を被う感じで調整していかないといけないので、そこもかなり細かい作業で難しかったです。
最後に素焼きまでして、色付けと本焼きを行う「常秀工房」さんに引き継がせていただきました。

色付け・本焼き後の鬼瓦
―普段のご自身の作風とは異なる作品を作るうえで感じた大変さや、そこから得た気づきなどがあれば教えてください。

普段、作品として作っているシーサーは自分の想像の中の生き物なので、こうした方がかっこよくなるんじゃないか、とその都度工夫して作っていて、決まった形があるわけじゃないんです。
でも今回の鬼瓦は、昔の資料を元に再現した原型というものがあって、その通りに作っていかないといけない。この “似せて作る” というのがけっこう難しかったですね。
時々監修が入るので「ここがちょっと違うね」と指摘いただいて修正したりということもありました。

石こう模型(原型)と新垣親子造形の鬼瓦
いつもは魔除けとしての怖いシーサー、力強いシーサーを作っているんですが、首里城の鬼瓦って、なんかみんなを見守っているような、ちょっとやさしい表情なんです。その表情を作っていく中で、こう作ればやさしい表情になるんだ、逆にこう作れば怖くなるんだ、という発見もありました。
あとは、これまで釜に収まる1mぐらいまでの大きさの作品しか作ったことがなかったので、今回の上下に分割して作る技術がすごく勉強になりましたし、今後大きな作品に挑戦したいなと思っています。
―シーサー職人という仕事の魅力や、やりがいを感じるのはどういったところでしょうか?

シーサーは沖縄の守り神であり、それぞれの家の守り神でもあるので、お客さんの家を守ったり会社を守ったり、そういう大事な役目を私が作ったシーサーが担えるということは、とても誇らしく思います。
私たちの魂とか気持ちだけではなくて、お客さんの思いがちゃんとのるような、「この子だったらしっかり家や会社を守ってくれるな」と思えるようなかっこいいシーサーをこれからも作っていきたいです。
―最後に、今回制作した鬼瓦と、復元される首里城に対する思いをお聞かせいただけますか?
今回制作したのは「鬼瓦」ではあるんですが、私は「シーサー」という気持ちで作っています。シーサーというのは元々「ヒーケーシ=火を返す」という願いを込めて、集落の入口などに作られたものなので、首里城でもう二度と火災が起こることのないようしっかり気持ちを込めて作っています。
それぞれの現場で関わった皆さんの思いや願いが込もった首里城になると思うので、2026年の完成が楽しみです。

取材日:2025年7月17日
他の記事はこちら
© Shurijo Castle Park All Rights Reserved.